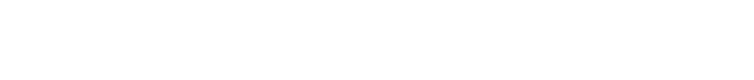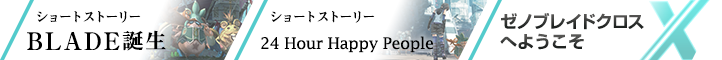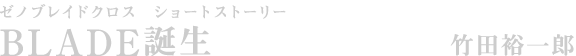徒歩で移動してきたヴァンダムと、ブリッジクルーたちがNLAに到着した。
「ほう、ニューロサンゼルスとは気のきいた名前をつけたもんじゃねえか」
「まあな。それより、だいぶ人数が増えているようだが──」
ヴァンダムが連れてきた顔ぶれを、ナギは見渡した。険しい道のりでブリッジクルーの誰かが脱落していないか心配していたのだが、どうやら見慣れない顔が加わっている。
「こいつらか? 途中でちまちま拾ってきた」
ヴァンダムの説明によれば、NLAに来る途上、いくつもの脱出ポッドを見つけたのだそうだ。
白鯨は巨大な移民船だ。当然、船体各所には強度の高いブロックもあれば、そうでないブロックもある。居住区やブリッジのような頑強なブロックは、船体が崩壊したときの衝撃にも耐え、重力制御装置によって軟着陸が可能だった。しかし、それが不可能なブロックも多かった。それらの区画にいたクルーは、それぞれ脱出ポッドに乗り込んで惑星地表に降下することになったはずだ。ヴァンダムはNLAへの道すがら、そうしたポッドを見つけ、中にいたクルーを救出してきたらしい。
「ポッドのことは俺も気になっていたが──」
「捜索する部隊を早めに編成した方がいいな。ほとんどのポッドは救難信号を発信しているはずだが、故障したヤツだってあるだろう」
ヴァンダムの言葉に、ナギはうなずいた。人命救助という観点だけでなく、貴重な人的資源を確保するためにも、ポッドで脱出したクルーの捜索は優先したい。落着時の居住区にいたのは非戦闘員が多かったため、白鯨の各所で異星人の追撃部隊を迎撃していた要員の確保は、特に重要だ。
「わかった。目的別に部隊を編成しよう。クルーや白鯨の遺物の回収、NLAの防衛、NLA周辺の調査──このあたりが最優先だな」
ドール部隊を中心にして、ナギはいくつかの部隊を編成、それぞれにテスタメント、インターセプター、パスファインダーという部隊コードを割り当てた。これらは後に八つの専門職へと整備されていき、ユニオンと呼称されるようになる。
ナギは自ら、テスタメント部隊を率いて、クルーの捜索に乗り出すことにした。NLAに居残り、インターセプター部隊の指揮をとるのはヴァンダムだ。これには大いに不満があるようで、ヴァンダムは食ってかかった。
「おい、あんたは船長だろう。総指揮官は本部でじっと待ってるもんだ。楽しい冒険を、可愛い部下から奪うもんじゃないぜ」
「楽しいというのは同意するが、可愛いというのには賛成しかねるな」
「そういうこと言ってんじゃねえ!」
ヴァンダムはゴネにゴネたが、最後は階級差にものを言わせて黙らせた。なんといってもナギは統合政府軍准将であり、ヴァンダムは中佐なのだ。
「ええい、こんな時だけ上官風ふかしやがって──!」
「いや、いつも上官面しているつもりなんだが、お前があまりにも部下面してくれないもんだからなぁ」
誰に対しても偉そうなヴァンダムのことはさておき、ナギには考えがあった。この先、NLAには指揮官が必要になる。政治、軍事、それぞれの中央と前線──とてもナギ一人では担いきれない。佐官以上の人間には、必ずいずれかを受け持ってもらわなくてはならない。ヴァンダムのような人物には、司令部で指揮をとる経験を積んでもらわなくてはならないのだ。
(まったく、エルマがいてくれれば──)
この星に降り立ってから、何度目になるかわからない言葉。ナギは口には出さないものの、考えずにはいられなかった。
NLAにあった稼働するドールのうち、AD0150 Formula.STを四機選んで、ナギはインターセプターを編成した。
「白鯨には、もっと高性能な機体も積んであったんだがな。格納庫ブロックを見つけ出すか、NLAで独自開発できるようにしたいもんだ──」
「お言葉ですが、重要なのは機体よりも搭乗者の腕。このメンバーなら、どんな過酷な任務だってこなしてみせますよ」
そう言って胸を張ったのは、ダグラス少尉だ。白鯨に乗っていたドール乗りのなかでも屈指の腕利きで、ともにいる二人も彼に引けをとらない優秀なパイロットたちだ。
「頼もしい言葉だな、ダグラス」
「よかったらダグと呼んでください、隊長。言葉だけでないことをすぐに証明してみせますよ」
「おお、そうか」
隊長と呼ばれて、ナギは気をよくした。将官などというものになって以来、現場に出ることも少なくなっていた。ブリッジで大型船の指揮をとるのもよいが、こうして少人数の精鋭チームを率いるというのも好ましい。
(いや、好ましいなどと考えるのは不謹慎だな。我々がいま置かれた事態の深刻さを考えればそんなことは言っておれん──)
そう思いつつも、つい頬が緩んでしまうナギであった。
作戦行動の第一目的は、脱出ポッドやライフの捜索だ。ナギは部隊を、ブリッジが落ちた場所と反対方向に向けた。ヴァンダムは粗雑に見えるが、実は細やかな仕事をする男だ。彼が捜索しながらやってきたルートに、生き残りのクルーはもういないだろう──という判断だ。
四機のドールは周辺警戒を密にしながら、探索行を続けた。その結果わかったのは、この惑星が驚異的な環境にあるということだ。重力を無視したかのような連峰が並ぶ奇観。多種多様すぎるほど豊かな生物相。
「他の惑星に来たのなんて初めてですけどね──自分の想像力がなんて貧しかったんだって、思い知らされてますよ」
「まったくだな。あそこにいる恐竜モドキを見てみろ」
ナギのドールが右手で指さしたのは、池の畔で水を飲んでいる恐竜にしか見えない生物だ。
「ああ、ブラキオサウルスに似てますね。たしか、地球で一億年以上前に生きていた──」
「その通りだが、俺が言いたいのはそういうことじゃない。さっき、あいつによく似たトカゲの群れを見たんだ。──子犬ほどの大きさのな」
「! 同じ生物が、そんなにサイズ差があるんですか!?」
「さあな、そう見えたというだけのことだから、事実はわからん」
驚いているダグにそう応えつつも、ナギは自分が感じたことが真実であると確信していた。どうもこの惑星の環境は、生物の遺伝子に過ぎたイタズラをする癖があるようだ。数日前、白鯨のブリッジを襲ってきた夜行性の生物のことを思い出す。あいつもたしか、大した大きさではない群れのなかに一匹だけ超巨大な個体が混ざっていた。サイズに見合う戦闘力を持っていたものの、それ以外は普通の個体と変わらないように見えた。あの時は、
物思いに沈んでいた時、最後尾をまかせていた准尉が報告してきた。
「隊長、熱源反応を確認しました。三時方向、二〇〇〇。なにかが炎上していると推定されます」
「山火事の類か──こんな距離でNLAに危険が及ぶとも思えんが、行って確認してみるか」
ナギは即決した。すぐに部隊の進路を右手に向ける。何もなかったらそれでいい、何もないということが確認できるだけで十分なのだから。
結果として、ナギの判断は正しかった。熱源反応を発していたのは、白鯨の遺物が炎上している現場だったのだから。巨大生物──オーバードに踏みつぶされたブロックには、運の悪いことに化学燃料が備蓄されていた。そこから発生した爆炎が白鯨の一部だったブロックを焼き尽くし、原生樹林にまで延焼したのだ。
炎から逃げ惑うクルーとともに、一人の移民がいた。彼の名はモーリス・ショーソン。補佐官として、大統領とともに白鯨に乗り込むはずだった政治家である。だが、埠頭に到着する寸前、異星人の部隊が地上を攻撃。彼らを乗せた車も、爆発に巻きこまれた。その後、意識を取り戻したモーリスは、自分が白鯨に運び込まれていたことを知る。大統領や同志たちの姿は、船内にはなかった。船内で治療が行われたという経緯が、操船クルーでもないのに、目覚めたまま乗客になるという状況を彼に与えることになった。
当初は罪悪感や無力感に苛まれたが、二年の旅は、モーリスに精神的な再構築の時を与えた。たしかに大統領を補佐することはできなくなった。
(だが、移民船が降り立つ新天地に亡き大統領やあの人の理念を根付かせることができれば──それこそが、生き残った私が果たすべき役割なのではないだろうか──)
モーリスはクルーたちの間を飛び回り、自分の理念を説いた。時には調停役として、トラブルを解決した。そうして、船の指揮系統とは異なる支持者層を築き上げていったのである。
(ミラ・トーレス──あなたの遺志、継いでみせましょう)
その人物はプロテスタントの聖職者であり、教育者であり、科学者だった。異星人による人類存亡の危機が迫るなか、地球種を移民させる計画の立案に尽力した人物の一人である。いや、その表現は正確ではない。立場としては地球種汎移民計画の委員のひとりに過ぎなかったが、彼女は間違いなく計画にとって精神的な支柱そのものだった。
予備委員会ともいえる有識者会議のメンバーのなかで、ミラはただひとり、異質な存在だった。国益や理念といった、それぞれが背負うものをどれだけ多く計画のなかに盛り込むことができるか──大半のメンバーの活動目的はそこにあった。そんな中で、ミラだけは人種や国家、宗教といったものを超越した計画立案に尽力したのだ。ある意味で、彼女は人類に対しても、肩入れはしなかった。人類以外のすべての地球種をも存続させることを目標にしていたのだから。
ミラというフラッグシップがいなければ、移民計画にあそこまで多くの支持が集まることはなかったかもしれない。彼女は文民を代表する立場にあり、軍人の共感を得られる人物でもあった。そして白鯨の出港間近、乗船を辞退すると、異星人に襲撃されている街へ向かい、炎の中で消息を絶ったのである──。
モーリスはミラという人物に私淑しながらも、理解できずにいた。彼女という求心力は、新天地でも必要だったはずだ。にも関わらず、移民船への乗船を拒否するなどと。
(現実問題として、彼女はこの惑星に来なかった。ならば、ここにいる誰かが、その遺志を継ぐしかないのだ──)
そう決意してはいたものの、遺志を継ぐためにはまず生き残らなくてはならない。オーバードと炎に追われ、モーリスはよろけつつも逃げ回った。見栄など気にしている場合ではない、死んでしまっては何も残せないのだ。
他のクルーたちが逃げ込んだ岩山の方へ向かおうとして、モーリスの脚がもつれた。激しく転倒する。膝を強打したのか、ひどく痛んで立ち上がれない。そんなモーリスの上に、影が落ちた。
巨大なオーバードがモーリスの目の前に立ち、恒星からの光を遮ったのである。
「あ、ああああ──」
モーリスは恐怖のうめき声をあげた。異星人に襲われた地球で生き残り、二年間、移民船のなかで支持者を増やし──そうして築いてきたものが、こんなところで潰えてしまうのだろうか。
その時だった、破壊音がしたのは。モーリスが音の方を見ると、オーバードもそちらを振り向いた。音を鳴らしたのは、どうやら何者かが炸裂弾を鳴らしたためらしい。
「でっかい──えーと、名前知らないからナントカさん! あなたの相手は私がします!」
それは少女の声だった。いや、声だけではない、見た目も十代前半の女の子だ。
「たしか、リンリー・クー──」
幼くして、メカニックを勤める天才少女のことを、モーリスも知っていた。人の名前と顔を覚えるのは政治家にとって初歩の心得である。
リンは様々な装備を持ち出して、オーバードの注意を引きつけようとしていた。装備の数々は、炎上するブロックから持ち出してきたものだろうか。メカニックとしての豊富な知識があるリンならではだ。
「さあ、こっちへ来なさい、ナントカさん!」
外見から年齢や力量を推し量るのは愚かなことだが、それでもモーリスは叫ばずにいられなかった。
「──逃げなさい、リンくん! 子供が大人の身代わりになろうなどと!」
「子供とか大人とか関係ありません! 走れる方が囮になる──これが正解です!」
立ち上がれずにいるモーリスに向かって、リンが叫んだ。彼女の気持ちが通じたのか、オーバードはそちらに向かっていく。
「わわわ、ホントに来た〜〜!」
モーリスからオーバードを引き離すように、リンは走り始めた。わざとジグザグに走っているのは敵の気をひきつけるためだろうか。
「私だって、せめて──」
モーリスは必死に這った。さっき逃げてくる最中に、誰かが放り出した通信機が落ちているのを見たのだ。あれを手にすれば、救援が求められる。交信可能域に誰かがいるならば、救援を求めなければ。誰もいないかもしれないが、それでもただ寝ているわけにはいかなかった。
高価な背広をズタズタにしながら、モーリスは這った。そして、通信機を手にする。震える指で、もどかしくも通信機能を立ち上げる。
「だ、だれか来てくれ──」
必死に呼びかけるモーリス。だが、救援の声は意外なほど高出力で──つまり、近距離から帰ってきた。
「こちらチーム・テスタメント、よく聞こえてますよ、補佐官殿」
声に少しだけ遅れて、轟音と震動が響いてくる。それは通信機越しにではない。モーリスは音の方を見た。そして、ナギが率いる四機のドール部隊の姿を見た──。
手練れのパイロットたちが乗ったドール部隊の戦闘力は凄まじかった。リンという少女を追い回していた巨大生物を包囲すると、手早く頭部を撃ち抜き、あっさりと制圧してしまったのである。
救われたリンとモーリス、そして岩山に逃げ込んだクルーたちがドール隊の近くに集まってくる。ナギたちもまた、機体を駐機姿勢にして、地面に降り立った。
「おかげさまで助かりましたぁ!」
元気な声とともに、リンが頭を下げる。そして、ナギたちの返事も待たずにドールの方へ向かっていった。
「おおお、このドール、AD0150 Formula.STですね! 最初はAD0130かと思ったけど、近づいてくる足音ですぐわかりました!」
などと言いながら、ダグ機右脚部の足首サーボモーターに詰まった砂利を取り除いている。
「どうやら根っからのメカニック気性らしいな」
「ええ、仕事だからいじってるんじゃなくて、触れることそのものが嬉しくて仕方ないってヤツですね。あの歳の女の子で、珍しいもんだ」
ナギとダグが笑い合う。そんな様子にも気づかず、リンは次の機体の様子を見に行っていた。
「──君は、ナギ船長だな。危ないところをたすけてもらって感謝する」
近くにいた青年に肩を貸してもらいつつ、モーリスがやってきた。
「いや、遅くなったことをお詫びします。大統領補佐官がご無事でよかった」
「私は正直言って、状況がよくつかめていないのだ。ここはどこだ? 白鯨はいったいどうなっている?」
そう問われて、ナギは思い出した。異星人の生体兵器群の襲撃を受けた時、説明を求めるモーリスをうっとうしく感じて、通信を途中で切り上げていたのだった。さすがにちょっと気の毒だったかもしれない。
ナギは率直に状況を説明した。白鯨船内に侵入した、生体兵器群は撃退したが、それで船体が損傷したこと。その後、未知の惑星の重力につかまり、地表に落着。その過程で、船体が崩壊、四散したこと。
「現在は、軟着陸に成功した居住ブロックを拠点として、各地に散らばったクルーや白鯨の遺物を捜索しています。私がその指揮をとっているというわけでして──」
「そうか、私もそこに──居住区に行ってかまわないかね」
「もちろんです、生存者は全員、あそこに集まってもらっています。ただ、あまり快適とは言えませんがね──」
「どういうことだ?」
現在の居住区はエネルギー不足で、十分な都市機能を維持できていないこと。アウターシェルの展開機能が大破して、外敵を防げないこと。それらの問題点をナギは説明する。
「それでも、荒野でキャンプするよりは、いくぶんかマシですけどな」
「あの──」
控えめな声の方を、ナギもモーリスも振り返った。ドールの内部フレームをいじった手でこすったのか、鼻の頭が黒くなっている。そんな顔でおずおずと、リンは告げた。
「エネルギー問題だったら、解決できるかもしれません──」
「なに、本当か?」
「はい、私見たんです。南に見えるあの山の向こうに落ちていったのを──あれは白鯨の主機関、DM機関です──」
![]()